M2下村あやが2025年12月9日~11日まで徳島県徳島市で行われた日本光学会年次学術講演会(Optics & Photonics Japan 2025)にて、第11回OPJ優秀講演賞を受賞しました。
広い角度で青色発色するモルフォ蝶の構造色は、鱗粉の特異なナノ構造によって説明できます。当研究室では、過去に本構造を模倣し、視野角依存性のない構造発色光輝材を開発してきました。 しかし、従来は多層膜を高さ方向に対して乱雑に配置するという、作製コストの高い方法により再現を行っていました。 そこで、本研究では多層膜表面へナノパターンを付与するという新設計により、従来型と同等の光学特性を維持しつつ構造単純化を実現しました。受賞
M2 下村あやが日本光学会年次学術講演会(Optics & Photonics Japan 2025)にて、OPJ優秀講演賞を受賞しました
桑原裕司教授がポーランドのウッチ大学からAmicoメダルを授与されました
桑原裕司教授が2025年5月に、ポーランドのウッチ大学(The University of Lodz)からMedal Amico(友情のメダル)を授与されました。
本メダルは、ウッチ大学との長期にわたる共同研究等への功績を讃える名誉賞として、学外の個人・企業などに授与されます。桑原教授は、これまでの国際的な研究協力、殊にLodz大学との協力における卓越した貢献を認められ、今回の受賞に至りました。 なお、本メダルが日本人の研究者に授与されるのは初めてのことであり、大変名誉ある結果となりました。
桑原裕司教授が日本表面真空学会「学会賞」を受賞しました
桑原裕司教授が2025年日本表面真空学会「学会賞」を受賞しました。本賞は、表面・真空科学の進歩発展、または学会の発展に、とくに顕著な貢献があった個人会員に授与されます。 受賞名は、「キラル分子に関するナノスケール分析手法の開発」です。
桑原教授は、走査トンネル顕微鏡(STM)を用いたSTM円偏光発光分光法(STM-CLE)と円偏光探針増強ラマン分光法(OA-TERS)という2つの異なる分光法を可能とする 解析システムを世界に先駆けて構築しました。これを用いて、キラル分子やカーボンナノチューブ(CNT)の実空間観察・電子状態解析・振動解析を行ってきました。 これらの研究を通して、分子がクラスター形成することで光学非対称性が反転・増大する現象を発見し、官能基の違いによりキラル認識のプロセスを制御可能なことを示すなど、 薬剤の不斉合成プロセスの高度化や光学デバイス開発への応用にも非常に重要な成果を挙げてきました。服部卓磨助教が応用物理学会にて講演奨励賞を受賞しました
服部卓磨助教が2024年9月16日~9月20日まで新潟県新潟市で行われた2024年秋季応用物理学会にて講演奨励賞を受賞しました。 2025年3月14日に行われた応用物理学会学術講演会内にて、表彰式が行われました。
走査トンネル顕微鏡(STM)の探針を用いた探針増強ラマン散乱(TERS)は、ナノスケールの空間分解能でラマン分光を取得することができます。 カーボンナノチューブ(CNT)と呼ばれるグラフェンシートを円周上に巻いたものは、その巻き方に応じて物性が異なります。ラマン分光はこのCNTの 巻き方を評価するために使われてきましたが、光の回折限界によって、その空間分解能は、数百ナノメートルの範囲にとどまっており、 個々の物性を評価することはできていませんせいた。そこで、本研究では、STMによる原子分解能測定と、TERS測定を用いることで、 ナノスケールから個々のCNTのラマンスペクトルを評価し、巻き方に応じて、ラマン強度の比が大きく変化することを明らかにしました。
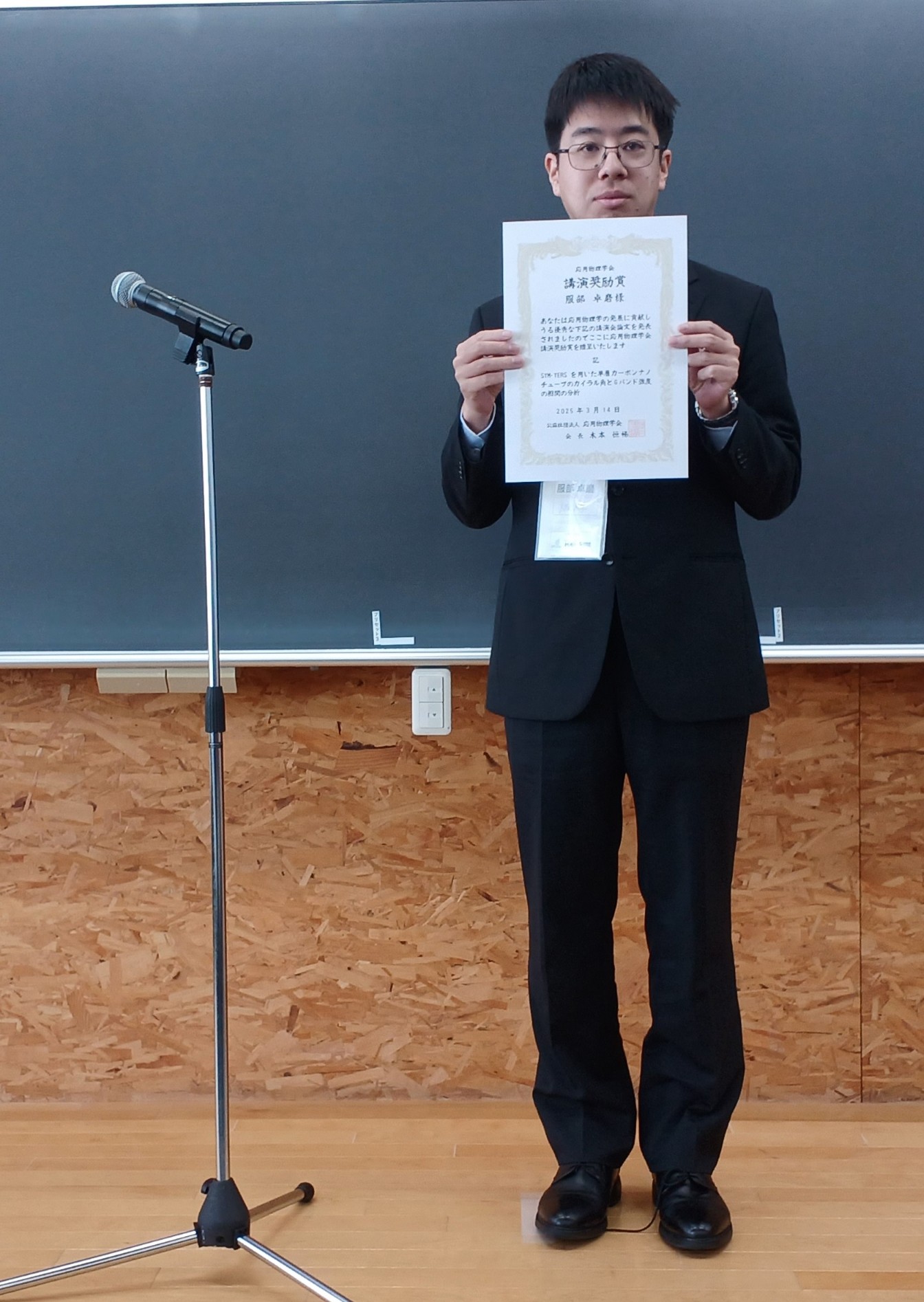

D3 Changqing YeがISSS-10にて学生賞を受賞しました
D3のChangqing Yeが2024年10月17日~10月20日まで福岡県北九州市で行われたISSS-10(The 10th International Symposium on Surface Science)で、学生賞を受賞しました。
ヘリセン分子は単純ならせん構造をもつキラル分子です。これまでに表面上に吸着したホモキラルのヘリセンジオールと、ラセミ体のヘリセンジオールで、 ほぼ同じ自己組織化構造が形成することを走査トンネル顕微鏡で確認していました。 本研究では、密度汎関数理論(DFT)と分子動力学計算(MD)を用いて、このヘリセンジオールの分子間に働く相互作用について評価しました。 MD計算とDFT計算を行うことで、実験で得られたヘリセン分子の自己組織化構造を再現し、分子間に働くヒドロキシ基の水素結合由来の相互作用によって ホモキラルの自己組織化構造が安定していることを明らかにしました。
